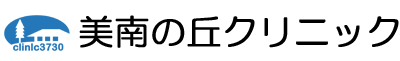睡眠時無呼吸症候群
日本の潜在患者数は300万人以上!?
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に呼吸が止まる病気です。
Sleep Apnea Syndromeの頭文字をとって、「SAS(サス)」とも言われます。
医学的には、10秒以上の気流停止(気道の空気の流れが止まった状態)を無呼吸とし、無呼吸が一晩(7時間の睡眠中)に30回以上、若しくは1時間あたり5回以上あれば、睡眠時無呼吸です。
寝ている間の無呼吸に私たちはなかなか気付くことができないために、検査・治療を受けていない多くの潜在患者がいると推計されています。
この病気が深刻なのは、寝ている間に生じる無呼吸が、起きているときの私たちの活動に様々な影響を及ぼすこと。
気付かないうちに日常生活に様々なリスクが生じる可能性があるのです。
睡眠中の酸素不足による脳や身体へのダメージ
本来、睡眠は日中活動した脳と身体を十分に休息させるためのもの。
その最中に呼吸停止が繰り返されることで、身体の中の酸素が減っていきます。
すると、その酸素不足を補おうと、身体は心拍数を上げます。
寝ている本人は気付いていなくても、寝ている間中脳や身体には大きな負担がかかっているわけです。
脳も身体も断続的に覚醒した状態になるので、これでは休息どころではありません。
その結果、強い眠気や倦怠感、集中力低下などが引き起こされ、日中の様々な活動に影響が生じてきます。
睡眠時無呼吸症候群
セルフチェック 私は大丈夫?
| Q1 | 「睡眠中に呼吸が止まっていた」と指摘されたことがありますか? |
|---|---|
| Q2 | 毎晩、大きなイビキをかきますか? |
| Q3 | 昼間、眠くなることがありますか?(居眠り運転をしそうになったり、会議中にうとうとしてしまうことがよくありますか?) |
| Q4 | 昼間、眠くなることがありますか?(居眠り運転をしそうになったり、会議中にうとうとしてしまうことがよくありますか?) |
| Q5 | 若い頃より、体重が増えて、顔つきが変わったと言われますか? |
| Q6 | メタボリックシンドロームの傾向はありますか? |
1つでも該当する場合、睡眠時無呼吸症候群の兆候があります。もっと細かくお調べしたい方は
簡易検査について
まずは問診から
ここで重要なのは、起きている間の自覚症状や生活状況について医師に伝えください。 昼間の眠気の自覚のほか、既往歴や体調変化、SASに特徴的ないびきの有無などの情報が診療に役立ちます。
自宅で睡眠中の状態を「検査」
問診の結果SASの可能性が疑われる場合には、具体的な検査へと進みます。自宅で普段通りに寝ながらできる検査が可能です。仕事や日常生活に支障を来たさずに検査を受けることができます。
自宅で手軽にいびきや呼吸をチェック

自宅でも取扱い可能な検査機器を使って、普段と同じように寝ている間にできる検査です。
手の指や鼻の下にセンサーをつけ、いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を調べます。
自宅でもできる検査なので、普段と変わらず仕事や日常生活をそれほど心配せずに検査することができます。
主に酸素飽和度を調べる検査(パルスオキシメトリー)と、気流やいびき音から気道の狭窄や呼吸状態を調べる検査とがあります。
要注意な症状が確認されたら
簡易検査では無呼吸の有無とその頻度を調べることはできますが、脳波や睡眠の深さなどの詳細データまではとることができません。
重症度によっては簡易検査の結果を受けてすぐに治療へと進むこともありますが、より詳細な精密検査が必要となる場合があります。
治療について
自分の状態と治療の意義を理解することが大切
多くの場合、SAS治療とは長い付き合いになります。
だからこそ、治療を始める前に自分のSASの重症度をきちんと把握しておくこと、治療の意義を十分に主治医と話し合っておくことが大切です。
ご家族やベッドパートナーの理解も心強いでしょう。
治療方法には、症状を緩和させるもの(対症療法)と、根本的にSASの原因を取り除くもの(根治療法)とがあり、いずれも個々の患者さんの状態に合わせて最適な治療方法が選択されます。
一概にどの治療方法が優れているということはなく、重症度や原因に応じた治療方法が適用されます。
治療とあわせて生活習慣も改善
治療方法に加えて、生活習慣の改善が必要になるのは言うまでもありません。
肥満気味の方の場合は首・喉まわりの脂肪が気道を狭くしている可能性がありますので、減量も治療の一環になります。
また、鼻づまりや鼻の諸症状で鼻呼吸がしにくい場合には、まず鼻症状の改善から取り組む場合もあります。
ここでは、代表的な対症療法の「CPAP治療」・「マウスピース」、根治療法の「外科的手術」の3つをご紹介しましょう。
対症療法1.CPAP療法

欧米や日本国内でもっとも普及している治療方法
「Continuous Positive Airway Pressure」の頭文字をとって、「CPAP(シーパップ)療法:経鼻的持続陽圧呼吸療法」と呼ばれます。
閉塞性睡眠時無呼吸タイプに有効な治療方法として現在欧米や日本国内で最も普及している治療方法です。
CPAP療法の原理は、寝ている間の無呼吸を防ぐために気道に空気を送り続けて気道を開存させておくというもの。
CPAP装置からエアチューブを伝い、鼻に装着したマスクから気道へと空気が送り込まれます。
「鼻にマスクをつけて空気が送られてくる状況で眠れるものなのか?」と思われるかも知れませんが、医療機関で適切に設定された機器を使い、鼻マスクを正しく装着できているかどうかが重要なポイントです。
そのため、医療機関に一泊入院して治療に適した機器設定を行う(タイトレーション)場合もあります。
治療は毎日のことなので、使い方でわからないことがあればコツをつかめるようになるまで主治医や医療機関のスタッフに相談してみると良いでしょう。
対症療法2.マウスピース

軽度な症状に適した治療法
睡眠時無呼吸症候群(SAS)を歯科装具(マウスピース)で治療するケースもあります。
スリープスプリントとも言われています。
下あごを上あごよりも前方に出すように固定させることで上気道を広く保ち、いびきや無呼吸の発生を防ぐ治療方法です。
作製は、SASについての知識があり、マウスピースや口腔内装置を作り慣れている専門の歯科医にお願いするのが良いでしょう。
マウスピースをつけて寝るだけ、と思うと手軽に思えるかも知れませんが、必ずしも全ての症例に効果的な治療方法というわけではありません。
中等症までの閉塞性睡眠時無呼吸タイプに対しては比較的効果が見られやすい一方で、重症の方の場合には治療効果が不十分とされる報告もあります。
重症度をきちんと把握し、主治医とよく相談した上で治療を始めるのが良いでしょう。
保険診療の適用になるかどうかは歯科医にご相談下さい。
*当院でマウスピースを作成することはありません。(歯科装具を取り扱う歯科で作成してください)
対症療法3.外科的手術
気道を塞ぐ部位を取り除く根治療法
小児の多くや成人の一部で、SASの原因がアデノイドや扁桃肥大などの場合は、摘出手術が有効な場合があります。
UPPPという軟口蓋(のどちんこ)の一部を切除する手術法もありますが、治療効果が不十分であったり、数年後に手術をした部位が瘢痕化してSASが再発することが少なくありません。
また、米国では狭い上気道を広げる目的で上顎や下顎を広げる手術も行われていますが、日本でこの手術を行える医療施設は限られています。